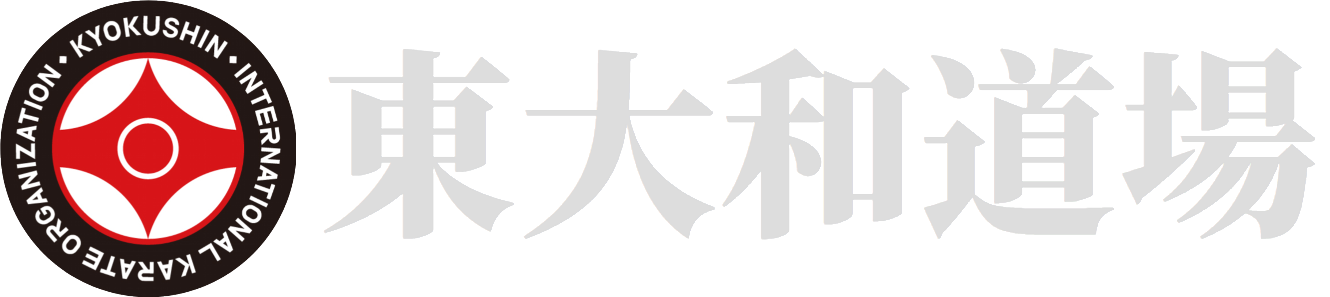〈土曜日少年部最初のクラス〉

土曜日最初の少年部達は幼年部達の稽古を軸に。
参加してくれる高学年達にとっても、御手本になったり、幼い後輩達に如何に伝わり易くアドバイスをして貰ったりも先輩達にも勉強になる。
意味のない場面は、実際に何一つとしてない。
全てが勉強となるはずだから。
〈以下、土曜日少年部2クラス目〉
【皆が何の為に極真空手をやっているのか、それを皆の何に活かしていくのか】を、一人一人に話を聞いた。
現段階、年齢による考え方を含めても、それぞれに共感の持てる内容ばかりを彼らは話してくれた。
指導者が明確な意志を持ちながら物事を教えていないと、子供達は本当に如何様にも変わる物だと思う。
支部長をはじめ、支部全道場で取り組んでいる少年部達への指導方針にも当て嵌まる。
競技の為だけの空手の指導ではないという事で、指導者側からすると、生徒達の試合の勝ち負けには、そこに必要以上に一喜一憂したり、ヤキモキしたりするという事も無い。
極真空手を通じて、生徒達のもっと更に先を見据えているからだと思う。
そこを軸に各道場それぞれのカラーがある。
焦らずじっくりとで全然良くて、仮に勝ったからと仲間達を下げる発言をしたり、上目線になる物では決してないという事で、それが正しいと履き違えてしまうと、最終的に長く続かないのが本当にオチ。
それに付随した部分を含めて、本当にじっくりと、彼らには一年中を話して説明をしている。

中学生になり、日々の稽古で確実に実力を増している田中千尋さん。




儀保彪瑚君の、空手に対するモチベーションも気持ちの強さも立派。
【なんか、彪瑚…組手、めっちゃ強くなってる…】と、煤賀昂誠君が、稽古後に爽やかな表情で後輩を称えていた。(先週の支部内組手試合では、煤賀昂誠君が小学2年生の部で初優勝、儀保彪瑚君は小学1年生の部で第3位に初入賞している)

試合を経験すると確かに皆が変わる。
勝っても負けても、そこから前向きに継続が出来る者達は本当にまた更に変わる事が出来る。

〈土曜日一般部選手稽古〉
金久保、湊さん、神代さん、多田君、平野さんで稽古した。
数年ぶりに平野さんが連絡をくれて、選手稽古に参加したいとの事で、神代さん、湊さんが素早く道場に足を運んでくれた。
神代さん、湊さん、平野さん、多田君も全員が仕事を終えた後に来てくれていた。
自分自身も含めて、おそらく全員が4、5年ぶりに組手稽古で、平野さんと手合わせをしたのではないかと思う。


組手稽古は90分間を全員でひたすら繰り返した。
かなりのラウンド数だったはず。
補強稽古、ウエイトトレーニングまでを合計3時間で稽古した。
いまだに日々のトレーニングを積み重ねている平野さんはスタミナは抜群だった。
【稽古は毎回が今の自分自身、今日の自分自身の確認の為の物でしかなく、そこには誤魔化しが一切通用しない物で、自分自身が一番感じ取る事が出来るし、仲間達にも、それらは全て伝わる物で、仲間達を通じて次に何が必要なのか、自分自身がどうしていくべきなのかを稽古を通じて知れる事が武道であり、格闘技であり極真空手の良さであり、それは日々の稽古も実戦の組手試合も全く同じ物でもあるという事、結局はそれぞれにとっての心身鍛錬の為の物でしかないという事】稽古後に、皆にそれを含めた話をした。
この部分て、子供達から大人達まで誰もが皆、同じだという事。
過去の人生での何かの栄光であったり、社会での現時点での立場や役職、それらは、共に稽古を積み重ねる場では、正直、何の効力すら発揮しないという物が無道であり格闘技だし、常に原点に戻り、己を振り返る事が出来て、仲間達とは無駄な利害関係が一切ない、クリーンな信頼関係を築く事が出来る物であり、極真空手とはそういう物だから。
俺自身、体調が良くない時や調子が上がらない時や稽古を休みたい時は実際に山ほどある。
むしろ、体を休ませろと言われても動かしてしまう性分だし、稽古をやるのかやらないのかは、結局は自分自身で決めるという事を人一倍に理解してもいる。
試合に出場し続けているのは、心の鍛錬の為であり、日々の稽古、仕事と捉えているからに過ぎないから。
俺自身が試合をせずに、自分の生徒達に精神論を伝えてあげる方法も勿論ある。
ただ、現役の選手であり、苦悩と葛藤を続けながら、常に自分自身と向き合っている事で、多くの生徒達へと伝えられる生の声が実際にある。
体が本当の本当に無理になるか、極真会館規定の一般選手終了年齢(50歳)になるかまでの勝負だと24時間考えて感じているし、どちらも限りが無く、もしも可能であるのなら、本当に永遠に続けていたいと本気で考えてもいるし、それって本当に物凄く幸せな人生だなとも感じている。
何事も一日一日の積み重ねでしかないという事。
その中で今日の自分自身と、どう向き合うのかという事だなって。
全てが勉強でもあり、凄く良い一日だった。
物事や仲間達に対する感謝の気持ちを忘れない。